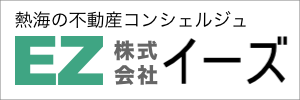【熱海・スナックと私 vol.3】 「釜鶴」社長・二見一輝瑠さん(後編:スナック「亜」)
特集「熱海・スナックと私」では、市内の経営者にお薦めのスナックを紹介してもらいながら、これまでの人生やこれからの経営ビジョンなどを伺います。聞き手は、熱海経済新聞副編集長でボイストレーナー「たーなー先生」としても活動する田中直人です。
3回目の今回は前回に続き、江戸時代から160年以上続く老舗干物店「釜鶴」5代目の二見一輝瑠(ひかる)さんです。1978(昭和53)年生まれで、現在46歳。熱海商工会議所青年部会長、熱海市観光協会理事、熱海富士後援会事務局長などを務める二見さん。家族との思い出やこれまでの歩み、会社経営、今後の熱海についてなど、気になる話を伺いました。
前回の記事
【熱海・スナックと私 vol.1】 「釜鶴」社長・二見一輝瑠さん(前編:スナック「キュウティー」)
【熱海・スナックと私 vol.2】 「釜鶴」社長・二見一輝瑠さん(中編:スナック「和み場ar侑」)
――3軒目に選んだスナック「亜」について、魅力などを教えてください。
二見 ちょうど自分が生まれた1978年にできた老舗スナックです。ママの手作りのお通しとホスピタリティーがすごくて熱海で愛されています。スナックでカラオケがないというのも珍しいと思います。
 釜鶴の二見さん(中央)と聞き手の田中(右)
釜鶴の二見さん(中央)と聞き手の田中(右)
――釜鶴の創業について教えてください。
二見 創業はおよそ160年です。元々は江戸時代から網元として漁業をしていました。網元だった祖先・釜鶴屋平七の像がムーンテラスのところに立っています。当時、マグロ網の権利を巡って網元と漁民の間で対立が深まり、騒動が起こりました。平七は、漁民の側に立ち、韮山代官所に漁師250人を連れて直訴しに行きましたが、これが一揆になって捕らえられてしまった。最終的に漁民側が勝訴するのですが、リーダーだった平七の罪は免れず八丈島流しになり、島流しの途中、伊豆大島で衰弱死してしまいました。正義のために弱い民衆の味方をしたということで、「釜鶴屋平七夫妻像」としてムーンテラスに銅像が立てられています。漁業権は失ったので、市場で魚を買って干物にする釜鶴としてのなりわいの始まりでもあります。
 ムーンテラスに立つ釜鶴屋平七の像
ムーンテラスに立つ釜鶴屋平七の像
――改めて、干物について教えてください。
二見 干物は食文化の一つ。塩蔵と乾燥の技術によって、長く魚を楽しんでもらう食文化です。自分が店を継いだ時に、岩塩や有名な塩などいろいろな物を試したのですが、ブラインドテイスティングしても違いが分からなかった。結局、今まで使ってきた塩を使い続けています。塩に漬けている時間は30分程度で、30分だとミネラルに違いは出ない。塩にこだわっても違いを感じられなく、魚の素材の良さを先にこだわることに行き着きました。地元の良い素材を使って干物にすることを今は大切にしています。ちなみに、塩分濃度はこの10年くらいかけて少しずつ変えてきました。
一般に流通している干物の多くは、旬のタイミングで取れた魚を冷凍し、それを1年間通して原材料として使っています。当店は主に地物の魚を干物にするので、根本的に材料が違います。その時に取れた魚を販売する魚屋さんと同じ感覚で干物を提供しています。
 干物のこだわりについて話す二見さん
干物のこだわりについて話す二見さん
――干物の魅力を伝える取り組みも続けていますね。
二見 干物造り体験を地元の保育園やイベント「おさかなフェスティバル」で続けています。当社で運営する「HimonoDiningかまなり」でも開き体験を開いています。
20~30代の人たちには、科学的な説明も加えながら、日本の伝統技術に基づいた干物の魅力についても意識して伝えるようにしています。干物の漬け汁の塩分濃度は、魚の浮く速度で分かるというようなことです。そうすることで、干物に対する見方が変わってきます。体験を通して日本の食文化の素晴らしさが伝わり、結果として店に対するロイヤルティーが上がってくると思います。
 保育園での干物造り体験
保育園での干物造り体験
――干物文化についての考え方を教えてください。
二見 干物は縄文時代から食べられていたという説もあります。平安時代や奈良時代には、干物が年貢として収められていた文献もあります。
熱海で干物の文化を継承していくためには、まずは干物を売る店がたくさんあることが大事だと思っています。駅を降りたら干物が目につくとか、商店街に干物が並んでいるとか。文化を受け継いでいる街であることが大切だと思います。
会社のパーパスには、海の恵みに感謝し還元するということを掲げています。漁師さんがいないと自分たちの商売は成り立たないので、漁師さんにもしっかり還元して大事にしないといけないことも社内では伝えています。
 「亜」の手作りのつまみ
「亜」の手作りのつまみ
――熱海の未来について、お考えを教えてください。
二見 熱海は第三の場所、観光と定住の間としてのサードプレイスが良いと思っています。仕事をする場所としてのファーストプレイス、家族と過ごす場所としてのセカンドプレイスがそれぞれあり、熱海はサードプレイスとして、それぞれの場所とは違う自分の居場所のような存在が合っているように思います。月1回でも週1回でも、いつ来ても安心できる街・熱海に将来性を感じます。そのためにも、店の魅力や店の人たちに受け入れる姿勢があることが大切だと思います。
自分自身は本年度、商工会議所青年部の会長を務めたり、まちづくりに関わったりしています。熱海の外の人と中の人をつなぐことも自分の役割だと思っています。地元の人だけで話をしていても進まないこともある。新しい人が外から入ってきて町の課題を一緒に考えていける環境を作っていきたいと思います。自分が住んでいて楽しい街にしないと面白くないですね。
熱海の課題としては、住環境や観光客に楽しんでもらうコンテンツ不足、食の質の向上が挙げられます。ただ、自分だけでできることは限られるので、地域が一緒になって実現していきたい。外の人から見ると熱海は可能性を感じる街に映っていると思います。自分は、熱海は「村」だと思っていて、この村社会に入る覚悟があるかどうかも大切です。昔から熱海にはたくさん外から人が入ってきた。ですので、熱海の人は目が肥えている人も多く、その人が本気かどうか見透かすことができてしまう。一升瓶を持って朝まで飲むくらいだと懐に入れる気がします。しっかり目的を持って本気でやろうという人には協力してくれる街だと思います。熱海自体を楽しみながら愛してくれるかどうかが大切です。やはり熱海のことが好きですから。
――3軒のスナックを回りながら二見さんの過去から現在、今後の展望を伺いました。ここまでありがとうございました。
 国産ウイスキーが並ぶ「亜」の店内
国産ウイスキーが並ぶ「亜」の店内
二見さんお薦めのスナック「亜」について
開業 1978(昭和53)年3月
ママ 佐保公己枝さん
席数 カウンター5席、テーブル4席
営業時間 20時~翌1時
定休日 不定休
住所 熱海市中央町6-4
電話 0557-82-3451
間もなく開業50年を迎える老舗スナック。現在のママ・佐保公己枝さんの母・しずえさんが創業。しずえさんは現在もほぼ毎週日曜はママとして店に立っています。カラオケはなく、落ち着いて会話を楽しむことができるスナックとして、地元で愛されるスナックの一つです。
過去の記事
熱海の老舗スナック「亜」が45周年 常連客が母と娘2代のママを祝う
 昔は遊郭だったという建物の名残を見せる「亜」外観
昔は遊郭だったという建物の名残を見せる「亜」外観
「釜鶴」過去の記事
熱海の「釜鶴」でサクラマスの「干物フレーク」 インターン生が開発
熱海の干物店「釜鶴」が干物開き教室 保育園児向けに毎年続ける
熱海の老舗干物店が新店「かまなり」 干物創作料理を8時から提供
聞き手:田中直人